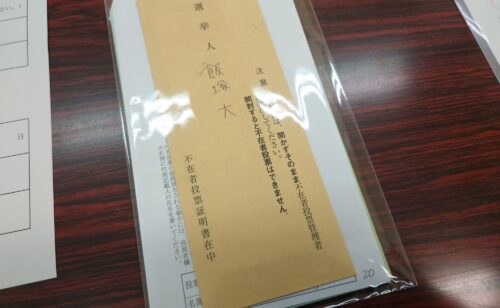コレ全部知ってたらベテランキャンパー?焚き火をもっと楽しむ薪の組み方6選
このブログはTOKYO CRAFTSが運営しています。TOKYO CRAFTSは《言語化できない満足感を。》をコンセプトに展開するコストパフォーマンスに優れた日本発のキャンプギアブランドです。
>> ブランドコンセプトを詳しくみる
当サイトの記事には広告、アフィリエイトが含まれています。
焚き火の火力をうまくコントロールすることは意外と難しいものです。
しかし組み方ひとつで火力の調整がしやすくなったり、薪の持ちが長くなったりすることはご存じでしょうか。
自然環境に対応した薪の組み方を考慮できると、一気にキャンプでの焚き火の楽しみが広がります。
今回は6つの薪の組み方を紹介し、最適な薪の組み方を考えてみます。ぜひ次回のキャンプで色々な薪の組み方で焚き火を楽しんでみてください。
薪の組み方ひとつをとってもこれだけの種類がある
薪の組み方にはたくさんの種類があります。
井桁(いげた)型
閉じ傘 (ティピ型)
開き傘(花火型)
差し掛け型(ジャンプ台型)
並列型(焚き火台型)
ロングファイヤー型
それぞれ写真とともにご紹介します。
①井桁(いげた)型(キャンプファイヤー型)
薪を『井』の字に組む定番の方法です。炎が高くあがるため、大人数でキャンプファイヤーを楽しむ際に、この組み方が使われます。
キャンプファイヤー型とも呼ばれることも。盛大に炎を燃やしたい方におすすめです。
【井桁型のメリット】
簡単で組みやすい
積み上げるほど煙突効果で燃えやすい
【井桁型のデメリット】
大量に薪を使う
②合掌型・閉じ傘(ティピ型)
閉じた傘のような形状から『閉じ傘』と呼ばれる組み方です。ネイティブアメリカンが使用していた移動式住居、ティピーテントに形が似ていることからティピ型とも呼ばれています。
空気を取り込みやすく、炎が美しく上がってくれるのがポイント。
最初に1本薪を横に置き、その薪を軸に組んでいくと組みやすいです。炎を観賞するならこの組み方がおすすめ。
【閉じ傘のメリット】
炎が美しく見える
【閉じ傘のデメリット】
薪のバランスがやや取りづらい
③合掌型・開き傘(花火型)
閉じ傘とは対照的に『開いた傘』のように見えることが名前の由来。打ち上がった花火のようにもみえ、花火型と呼ばれることもあります。
焚き火台中央に着火、先端からジワジワと燃えていくので長時間、それも少ない薪の量で焚き火を楽しめます。ただし、火が消えないように薪の世話がやや大変。
【開き傘のメリット】
薪の消費が少なくて済む
【開き傘のデメリット】
大きめの焚き火台でないと組めない
④差し掛け型(ジャンプ台型)
1本の薪を枕木(土台に据え置く薪)にして、立てかけるように薪を並べる組み方。
枕木と立てかけた薪の間の空間に、焚き付けや火種をいれて燃やします。立てかけた薪が斜めに伸びていく様子から、ジャンプ台型と呼ばれることも。
焚き火台マクライトであれば、両側の風防を枕木にみたてて、薪を立てかけることで同様の組み方ができます。
【差し掛け型のメリット】
枕木があるので安定する
簡単に組めて手軽
【差し掛け型のデメリット】
枕木に大きめ(太め)の薪が必要
⑤並列型(焚き火台型)
枕木を2本設置してその上に橋をかけるように、薪を並べていく組み方。面の広い焚き火台のような形から、焚き火台型とも呼ばれています。
横に並べた薪が平らなので、クッカーを置いて調理しやすいのが特徴です。
直火で焚き火する際には、地面が濡れていても着火しやすい点がこの組み方の優れたポイント。並列に並べた薪を火床にして、そのうえに焚き付けをおいて着火します。
【並列型のメリット】
環境に左右されずに着火できる
面が平らで広いので、調理しやすい
【並列型のデメリット】
狭い焚き火台ではやや難しい
⑥ロングファイヤー型
太めの薪を2本並べてその間に細い薪を平行に配置する組み方です。
野営でもよく好まれるこの薪の組み方は、左右から風を遮ることができる上に、火床が安定しているため、焚き火調理に向いています。
焚き火台マクライトを使用する場合、両側の風防が2本の太い大きな薪の役割を兼ねられます。
簡単ですが、横に薪を並べただけのこんな組み方もアリです。
【ロングファイヤー型のメリット】
焚き火調理しやすい
【ロングファイヤー型のデメリット】
特になし
スタッフがイチオシだった薪の組み方はコレ。
スタッフが実際にやってみて良かった組み方は「差し掛け型(ジャンプ台型)」と「ロングファイヤー型」。
差し掛け型(ジャンプ台型)は簡単に薪を組めるうえに、意外にも空気の通りがいいので、よく燃えてくれます。
薪の継ぎ足しもほどよく、自分で炎を育てていく感じが適度に楽しめるはずです。
▼差し掛け型。太い薪にいくつか薪を立てかけるだけ。
一方で、ロングファイヤー型は焚き火調理にチャレンジしたい方にはぜひ試していただきたい薪の組み方です。
2本の薪に囲まれた場所には熾火がたまっていき、程よい火力に。
熾火の状態であれば、少し積み上げて高さを出してあげることで、場所ごとに火力の強弱を意図的につくれます。
▼ロングファイヤー型。太い薪の間に細い薪を配置するとクッカーが安定する
焚き火台の火力調整に困っている方はぜひトライしてみてください。
薪の組み方は、好みや気分、そのときの環境によって変えるのが焚き火の楽しみの醍醐味。
ぜひいろいろな組み方を試していただき、自分がしっくりくる焚き火を追及してみてくださいね。
以下の動画でも焚き火のやり方を解説しています。ぜひ参考にしてみてください。